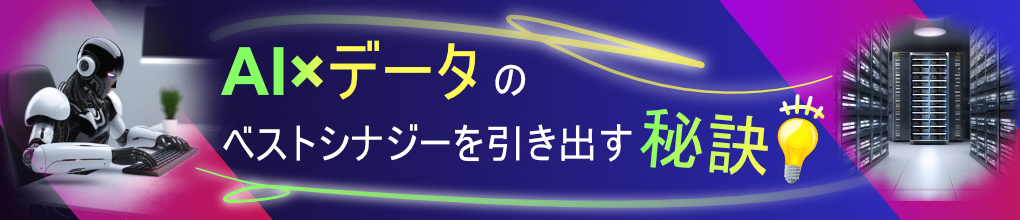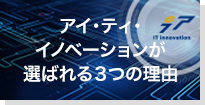生成AI vs 予測・分析AI
~現場で迷わない「使い分けガイド」~
AIを導入しようとすると、「この課題は生成AIで解くべきか? それとも分析・予測AIか?」で悩む企業は多いです。生成AI(LLMやRAGなど)は文章や会話の生成が得意であり、分析・予測AIは需要予測や人流の予測など、数値の将来予測に強みがあります。どちらも強力な技術ですが、活用領域を見誤ると成果が出にくいという落とし穴があります。
そこで、この記事では、迷わず判断できる「使い分けの型」をまとめています。
1. 生成AIと予測・分析AIの違いを整理
まずは、両者の違いを俯瞰してみましょう。
| 観点 | 生成AI | 分析・予測AI |
|---|---|---|
| 得意分野 | 報告書作成、FAQ、商品説明、レポート、ナレッジ検索 | 需要予測、品質・不良検知、人流予測、スコアリング |
| 入力データ | 文書・規程・商品情報・FAQなどのナレッジ | 売上高、発注量、センサ、顧客行動などの数値データ |
| 出力 | 文章・会話・根拠リンク | 数値・確率・アラート |
| 評価指標 | 正確性/網羅性/一貫性 | MAPE/AUC/R2 |
| 運用ポイントの例 | プロンプト設計、チャンク | モデル再学習、推論AIと実績の監視、モデルデプロイ |
<ポイント>
文章・会話を自動化したいなら生成AI、数値判断や最適化をしたいなら分析・予測AIが基本です。
2. 迷ったときに使える「判定ツリー」
次の5つの質問に答えると、どちらを使うべきかが見えてきます。
【Q1】目的は「過去のデータをもとに未来を予測したい」ですか?
- YES → 分析・予測AI
例:売上予測、需要予測、異常検知、不良率予測、顧客離反の予測 - NO → Q2へ
【Q2】目的は「新しいアイデア・文章・画像などを作り出したい」ですか?
- YES → 生成AI
例:文章生成、画像生成、コード自動生成、プレゼン資料作成、文章要約 - NO → Q3へ
【Q3】求める結果に「正確な数値や確率」が必要ですか?
- YES → 分析・予測AI
例:予測スコア、確率、数値的な傾向分析 - NO → Q4へ
【Q4】入力データが「数値・ログ・センサー情報などの構造化データ」ですか?
- YES → 分析・予測AI
例:製造装置データ、販売実績、顧客行動ログ - NO → Q5へ
【Q5】入力データが「テキスト・画像・音声などの非構造化データ」ですか?
- YES → 生成AI
例:文章や画像の要約、自然言語での問い合わせ応答、デザイン提案 - NO → 分析・予測AI(またはAI不要)
3. 技術的な動向の違い
分析・予測AIと生成AIを技術的な観点で見ると、どちらも機械学習をベースにしていますが、扱うデータや目的、そして学習の仕組みはまったく異なります。
■ 分析・予測AIのAIモデル学習フロー
<学習フェーズ(自社基盤)>
自社で蓄積した大量の学習データをAIモデルに投入し、パターンを学習させます。
→ 未学習のAIに「会社固有の特徴」を覚えさせる段階です。
<推論フェーズ(自社基盤)>
新しいデータ(入力)を与えると、学習済みモデルが予測値や判断結果(出力)を返します。
例えば、「次月の売上予測」「ユーザーが購入しそうな商品」など。
■ 生成AIのAIモデル学習フロー
<事前学習フェーズ(他社基盤)>
GPTやClaudeなど、他社が大規模データで学習済みのAIを基盤として使用。
すでに「言語知識」を持っているAIを利用できるのが特徴です。
<推論フェーズ(自社データ連携)>
入力文(質問など)をもとに、AIが検索・参照・生成を行います。
最近では、RAG(Retrieval-Augmented Generation)という手法が一般的で、自社のドキュメント検索と組み合わせて回答精度を向上させます。
これらをまとめると下表のようになります。
4. まとめ
AI導入の成功は、「どのAIを使うか」ではなく、
「どの業務で、どのように使うか」を定義することから始まります。
生成AIは文章・ナレッジ・説明を生み出す力、予測・分析AIはデータから判断・最適化する力であり、両者を適材適所で組み合わせることで現場の知恵とデータの力を掛け合わせた新しい意思決定の形が生まれます。
迷ったときはまず、この記事の「5問チェック」で活用の方針を決め、次にRACI表等で責任と承認フローを整理してください。
これだけでもPoC(試行)止まりから脱却し、成果を出すAI活用へ一歩進むことができます。
(おまけ)
少しだけおまけの話を。。。
過去の案件の延長で、「アバターAI」を試作しました。社員一人ひとりの業務ナレッジと会話スタイルを学習させ、まるで<自分の分身>のように対話を行うAIです。
最初は「自分の分身なんて作れるの?」と半信半疑でした。もちろん、完璧ではなく、まだ「癖の再現」、「適切な会話量」、「感情の理解」など、人らしさの領域では改善が必要です。しかし、色々とやってみると、将来的にはAIが「人の判断を支えるパートナー」へ確実に進化できると思うようになりました。
「正しいAIの使い分け」は、まさにこの「人×AIの共創」を実現する第一歩となります。生成AIが持つ“表現力”と、予測・分析AIが持つ“判断力”を組み合わせることで、人の思考を拡張するAIが現実になりつつあると強く感じました。
アバターAIは下の動画をご参照下さい。